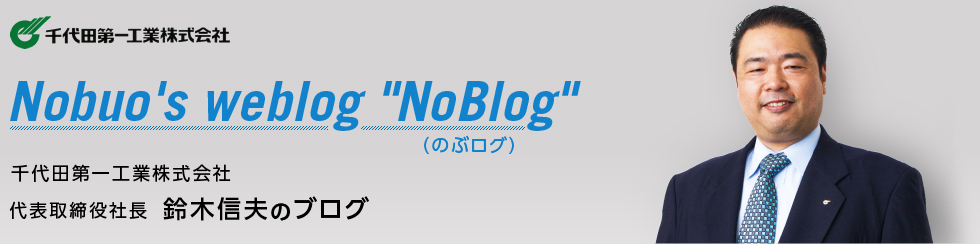事業の継続とは??
過日、群馬県で塑性加工の研究会と工場見学に行ってきました。
老舗の塑性加工を行う工場のM&Aのお話しと、新規事業。そして、富岡製糸場に伺って、帰って参りました。
所謂「研修旅行」とは違って、内容が濃かったわけですが、とても勉強になりました。
M&Aには必ず、売り側と買い側があるわけですが「所謂経済学の言うところの情報の非対称性」※を地で行くような内容でした。友人に買う方も売る方も居たわけですが、それらの情報より、生々しい話を聞くことができて、とても勉強になった次第です。
次に、製造業の会社が”「食物工場」を始めた”と、いうことで、見学に行って参りました。

色々な手法 があるわけですが、”「食品工場」の機器を販売する商社”の製品プラス現在まで、自動車業界で培ったQCの手法を取り入れて、色々な挑戦をされていました。所謂経営学の言うところの「両利きの経営」※2を挑戦されているのですが、聞いたときは「????」だったのですが、工場を拝見して「やっぱり工場なんだ」と、思いました。(笑)しかし、天候に左右されるとは言え、エネルギーを使わない一般的な「農業」と戦わなければいけない。製造業では、製品の差はとてもわかりやすい(材質、幾何学交差、性能等)ですが、この分野は「感情」みたいなものが重要なわけで、仮説を持って取り組んでいる姿がとても印象的でした。
最後に、富岡製糸場に伺ってきたのですが、お伺いして驚いたことが「生糸も化繊もラインの作り方は粗同じである」事でした。詳細はマニア過ぎるので割愛しますが、例えば、現在もフィルムや繊維のラインは「片持ち」と呼ばれるローラーは片方で支える仕組みになっています。「糸切れしたときに、再度糸が掛けやすい」という話ですが、現在の高速ラインでそうそう糸やフィルムがキレるわけでもございません。しかし、昔のラインを見ると、何分生糸ですから、頻繁に糸が切れますし、ラインが止まらないように、紡ぐ作業が必要となります。このラインをみて、現在のラインに脈々とノウハウが引き継がれていることが理解できました。
話を戻しますと、この一日で感じたことは「かくも事業を継続するということが難しいのか!」という事です。規模の経済性を求め「時間を買う」事を目的にM&Aを試みても、目論見通りに行く事も少ないですし、既存の市場に、新しい商品をぶち込んでも、消費者や流通はそうそう現在までの商流を変えることは望んでいません。そして、世界を席巻して、完成したラインを構築しても、代替品が出て来たり、コストメリットが失われれば、街ごと無くなってしまう。。。。。以前は「選択と集中」と言われたものですが、GEを代表するようにそのような企業が現在の状況であることを考え合わせると、やはり「両利きの経営」をせざるを得ないということが理解できた次第です。
弊社は73期を迎えました。立ち止まることは出来ません。限られた時間と資本の中で「両利きの経営」を行っていきたいと思います。
それでは、失礼します。
※ノーベル経済学賞(2001年)を受賞した「情報の非対称性」理論の事。に関する研究で ジョージ・アカロフ (George Akerlof)「レモン市場」、マイケル・スペンス (Michael Spence)「モラルハザード」、ジョセフ・スティグリッツ (Joseph Stiglitz)「シグナリング」を指しています。
※2チャールズ・オライリー (Charles A. O’Reilly III)
スタンフォード大学経営大学院(Stanford GSB)の教授であるチャールズ・オライリーが提唱した「両利きの経営」(Exploration and Exploitation in Organizational Learning” 1991)及びハーバードビジネススクールの教授であるマイケル・タッシュマンが提唱した「探索」と「深化」(The Ambidextrous Organization”2004)を指します。「探索(Exploration)」と「深化(Exploitation)」の双方向が重要であるという理論であると認識しています。
ダイクロンやブラストロンのことなら
千代田第一工業株式会社へ